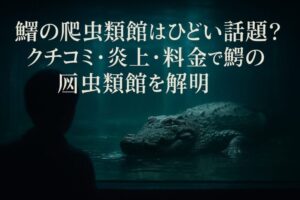ドテラやめたほうがいいと検索する人は、何かしらの不安や疑問を抱えていることが多いです。
やめた理由や後悔の声、健康への危険性、厚生労働省や消費者庁の見解、さらにコンプライアンス違反の事例や勧誘がしつこいといった口コミまで、ネットにはさまざまな情報があふれています。
実際に友達なくすほど人間関係に影響したという声もあり、ネットワークビジネスの仕組みや評判を理解しておきたいと考える人が多いのも納得です。
この記事では、そうした不安を整理し、冷静に判断できるようにまとめていきます。
- ドテラをやめた理由や後悔の具体例
- 危険性や厚生労働省と消費者庁の見解
- 勧誘や人間関係のトラブルの実態
- ネットワークビジネスの仕組みと評判
ドテラやめたほうがいいと感じる背景


- やめた理由として多い声
- 続けて後悔したケース
- 製品や使用法に潜む危険性
- 厚生労働省との関係性
- 消費者庁からの注意点
やめた理由として多い声


ドテラをやめた人の理由を探ると、もっとも多く挙がるのは経済的な負担です。ドテラのエッセンシャルオイルは「高品質」とされる一方で、他社の精油と比較して価格が高めに設定されています。例えば、ドテラの人気オイル1本(15ml)は数千円〜1万円を超えることもあり、定期購入プログラムを利用すれば毎月1万〜2万円近くの出費になるケースも少なくありません。これが長期的には家計を圧迫する大きな要因となります。
さらに、ドテラはネットワークビジネス(MLM)の仕組みを採用しています。これは、自分が購入するだけでなく、新規の会員を紹介していかないと収入が伸びにくいという構造です。紹介が上手くいかない人にとっては、出費だけがかさみ、報酬はほとんど得られない状況になりがちです。経済的にマイナスが続くと、「やめよう」と考えるのは自然な流れです。
もう一つの大きな理由は、人間関係への悪影響です。ドテラを続けるには製品を紹介する必要があるため、友人や家族、同僚に勧誘せざるを得なくなります。その結果、関係がぎくしゃくしたり、信頼を失ったりすることが多く報告されています。特にママ友や近しい人間関係の中での勧誘は、相手からすると「付き合いづらい」と感じさせる要因になります。
こうした経済的な負担と人間関係の摩擦が重なり、多くの人が「やめてよかった」と振り返っているのです。つまり、やめた理由は単一ではなく、金銭・精神・人間関係の3つの側面が複雑に絡み合っているといえます。
| 主な理由 | 典型的な具体例 | 背景・発生メカニズム | 想定されるリスク | 参考情報(一次情報) |
|---|---|---|---|---|
| 経済的負担(定期購入・価格) | 割引やポイント目的で毎月複数本を継続購入し出費が固定化する | 会員制度やロイヤルティリワードプログラム(LRP)など継続購入を前提とした設計 | 家計の圧迫、在庫滞留、解約・返品手続きの負担 | doTERRA 公式:会員登録情報 doTERRA 公式:LRPの概要 |
| 収益性の低さ・期待とのギャップ | 紹介が伸びず報酬が増えない一方で自己購入費用のみかさむ | 連鎖販売取引は組織拡大と購買量に報酬が依存し、下位層は収益化が難しい構造 | 収入より支出が上回る赤字、活動継続の動機低下 | 消費者庁:マルチ商法って? |
| 勧誘による人間関係の悪化 | ママ友・同僚・親族への継続的な誘いで疎遠化や摩擦が生じる | 販路が身近な人間関係に依存し、断りづらさや同調圧力が生まれやすい | 友人関係や職場の信頼低下、生活面でのストレス増大 | 消費者庁:連鎖販売取引(特商法ガイド) |
| 使用法の誤解による健康・法規リスク | 飲用や原液塗布の安易な推奨、効能を断定する説明 | 医薬品ではない製品に医療的な効果を連想させる表現が拡散しやすい | 皮膚トラブルなどの健康被害の恐れ、薬機法の広告規制に抵触する恐れ | 厚生労働省:医薬品等適正広告基準(PDF) |
| コンプライアンス不安(統制・手続き) | SNS等で不適切表現が拡散、解約・返品を巡る認識違いで紛争化 | 分散型販売で表現統制が難しく、特定商取引法のルール理解不足が生じやすい | ブランド信頼の毀損、行政指導・契約トラブルへの発展 | 消費者庁:連鎖販売取引(特商法ガイド) |
続けて後悔したケース


ドテラをやめずに続けた結果、後悔するケースも少なくありません。代表的なのは、収入がほとんど得られなかったにもかかわらず、購入費用だけがかさんでしまうパターンです。ネットワークビジネスの収入モデルでは、上位にいる一部の人が多くを得る構造になっており、下位層にとどまる人の収益はごくわずかという実態が指摘されています(参考:消費者庁「連鎖販売取引に関する注意喚起」)
家計の中で数万円単位の出費が固定化すると、日常生活に大きな負担となり、精神的なストレスも増加します。「もっと早くやめておけばよかった」という声が多いのは、経済的な損失だけでなく、時間や人間関係まで犠牲にしてしまったと感じるからです。
さらに、後悔の理由には「期待していたほどの効果がなかった」というものもあります。精油の香りや使い心地に満足していても、「これで収入が得られる」と思っていた期待が裏切られた時に強い失望感を抱く人が多いのです。オイルを楽しむだけならシンプルに購入すればいいものを、ビジネスとして抱え込んだために「自分で自分を追い詰めてしまった」と後悔する例も目立ちます。
| 後悔の主なパターン | 具体的事例 | 背景・仕組み | 起きやすい影響 | 参考情報(一次情報) |
|---|---|---|---|---|
| 家計の圧迫と在庫滞留 | 毎月100PV前後(約1.2万〜1.5万円相当)の自己購入を続けて出費が固定化し、未開封ボトルが増える | ロイヤルティ・リワード・プログラム(LRP)等で継続購入を前提にポイント還元が設計される | 赤字継続・在庫リスク・解約時の心理的ハードル増大 | doTERRA Japan 公式サイト 消費者庁:連鎖販売取引ガイド |
| 収益が伸びない構造的ギャップ | 紹介が増えず報酬は数百〜数千円の月もあり、自己購入費を下回る | 連鎖販売取引は組織の購買量依存で、下位層ほど収益化が難しい | 活動コスト先行・時間投下に対する費用対効果の低下 | 消費者庁:マルチ商法って? |
| 人間関係の摩擦・疎遠化 | ママ友・同僚・親族に繰り返し勧誘して関係が気まずくなる | 販路が知人ネットワーク中心で断りづらさや同調圧力が生じる | 友人関係の断絶、職場での評価低下、孤立感の増大 | 消費者庁:注意喚起・相談事例 |
| 使用法の誤解による健康・法規リスク | 飲用や原液塗布を安易に推奨し、皮膚トラブルや誤飲リスクが懸念される | 医薬品ではない製品に医療的効能を示唆する宣伝は規制対象 | 健康被害の恐れ、薬機法の広告規制に抵触する恐れ | 厚生労働省:医薬品等適正広告基準 AEAJ:精油の安全性ガイド |
| 解約・返品手続きで消耗 | 定期購入の停止手順や返品条件を把握できず、対応に時間を要する | 会員種別や申請期限、条件(未開封・期間など)の理解不足 | 手続き負担・返金遅延・トラブル化のリスク | doTERRA Japan:法定表示・購入規約 消費者ホットライン188 |
| 時間・メンタルの消耗 | セミナー参加やオンライン説明、SNS運用などで休日・夜間が埋まる | 組織維持のための活動が継続的に発生し、成果が見えにくい | ワークライフバランス悪化、燃え尽き、自己肯定感の低下 | 消費者庁:連鎖販売取引(特商法ガイド) |
製品や使用法に潜む危険性


ドテラのエッセンシャルオイルは公式に「CPTG(Certified Pure Tested Grade)」という独自の品質基準を掲げており、製品検査や原料管理を行っていると説明されています。しかし、ここで注意しなければならないのは、厚生労働省や食品安全委員会などの公的機関が「飲用に安全」と保証しているわけではないという点です。日本国内で医薬品としての承認を受けているわけではなく、効能効果をうたえば薬機法違反につながる可能性もあります(出典:厚生労働省「医薬品等の広告規制」)
また、エッセンシャルオイルは非常に濃縮されているため、肌に直接使用する場合には希釈が必要です。敏感肌の人やアレルギー体質の人は、パッチテストを行わずに使用すると炎症やかゆみを起こすリスクがあります。実際に口コミの中には「肌が赤くなった」「香りが強すぎて頭痛がした」といった体験が多数報告されています。
さらに問題なのは、勧誘の場面で「オイルを飲めば健康になる」「病気が改善する」といった表現が安易に使われることです。これは医学的根拠に乏しく、誤った使い方による健康被害を招く危険性があります。エッセンシャルオイルを楽しむ方法自体は安全にできるものですが、正しい知識を欠いたまま誇張した説明が広まるのは消費者にとってリスクが高いといえます。
| 主な危険性・注意点 | 具体例(精油・状況) | 推奨される対策 | 対象・場面 | 参考情報(一次情報) |
|---|---|---|---|---|
| 飲用・内服によるリスク | 精油を水や飲料に入れて摂取する等の誤用 | 日常的な飲用は避けるとされる。医療目的は医師の管理下での判断が前提 | 全年齢。特に子ども・妊娠中・基礎疾患のある人 | AEAJ 精油の安全性ガイド 厚生労働省 医薬品等適正広告基準(PDF) |
| 皮膚刺激・感作(アレルギー) | オレガノ、シナモンバーク、クローブ等の強刺激性精油を原液塗布 | 植物油で適切に希釈(目安1%前後)、パッチテスト、刺激部位・粘膜は避ける | 敏感肌・アレルギー体質・子どもへの塗布時 | AEAJ 希釈・皮膚感作に関する注意 |
| 光毒性(フォトトキシシティ) | ベルガモット、グレープフルーツ、レモン(FCF除く)を塗布後に日光・紫外線暴露 | 塗布12〜24時間は日光・日焼けマシンを避ける。光毒性の少ない精油やFCF品の選択 | 外出前のボディ・ハンドケア、マッサージ使用時 | AEAJ 光毒性の注意喚起 |
| 小児・妊娠・授乳での留意 | 乳幼児の誤飲、過度な拡散、妊娠初期の高濃度使用 | 乳幼児は低濃度・短時間拡散、十分な換気。保管はチャイルドロック。妊娠中は専門家へ相談 | 家庭内使用・ベビールーム・産前産後ケア | 日本中毒情報センター(誤飲対応) AEAJ 年齢別の使用目安 |
| ペット(特に猫・小動物)への影響 | 猫の代謝機能に負担、犬の嗅覚過敏でストレス | 直接塗布・飲用は避ける。使用時は換気し、動物が逃げられる環境を確保。獣医師に相談 | 室内飼育環境でのディフューズ、グルーミング時 | AEAJ 動物と精油に関する注意 |
| 引火性・保管・誤混和 | 可燃性溶媒としての精油を火気近くで使用、直射日光・高温下で保管 | 火気厳禁、遮光ビンで密栓し冷暗所保管、子どもの手の届かない場所に保管 | アロマキャンドル併用、キッチン・暖房器具周辺 | AEAJ 保管・取扱いの基本 |
| 効能表示・広告表現の法規制 | 病気が治る・予防できる等の断定的表現 | 医薬品と誤認させる表示は避ける。体験談の強調にも注意 | 販売ページ・SNS・勧誘時の説明 | 厚生労働省 医薬品等適正広告基準(PDF) 消費者庁 景品表示法の考え方 |
| 食品添加物と効能の誤解 | 一部精油の食品添加物登録を「健康効果の保証」と誤認 | 食品添加物は香料等の用途限定とされる。摂取量や用途を逸脱しない | 飲食物への利用・レシピ提案時 | 厚生労働省 食品添加物制度 |
厚生労働省との関係性


ドテラのエッセンシャルオイルは、日本国内では厚生労働省から医薬品や食品として正式に認可されているわけではありません。一部の製品は「食品添加物」として登録されていますが、これはあくまで食品に香り付けする用途に限られた認可です。つまり「飲んでも安全」「病気が治る」といった効果を厚労省が保証しているものではありません(出典:厚生労働省「食品添加物公定書」
消費者が誤解しやすいのは、この「食品添加物登録=安全に飲用できる」という認識です。実際には、添加物は基準量や用途を厳密に守ることが前提であり、健康効果を目的に摂取するものではありません。厚労省も「健康被害を防ぐために誤解を招く広告や説明は避けるべき」と注意を促しています。
また、日本国内のアロマセラピーの位置づけは「リラクゼーションや生活の質向上を目的とする補完的な活用」にとどまっています。医療分野で活用する場合は臨床アロマテラピーのように医療従事者の監督が必要です。ドテラの勧誘で「体調が改善した」「病気に効果がある」といった表現が出てくることがありますが、これらは厚労省の認可範囲を超えた誤解を招く表現である点に気を付ける必要があります。
| 論点 | 厚労省での位置付け | 具体的な意味合い | 消費者の留意点 | 公式情報(一次情報) |
|---|---|---|---|---|
| 医薬品承認の有無 | 多くの精油は医薬品ではなく化粧品または雑貨の扱い | 医薬品としての効能効果は承認されていない。疾病の治療や予防を標榜できない | 治る改善する等の医薬品的表現は誤認リスク。用途はリラクゼーションなどに限られる | PMDA 医薬品等の範囲に関する基準(PDF) 厚生労働省 薬機法の概要 |
| 食品添加物としての扱い | 一部の香料は食品添加物として指定可能 | 食品の香り付けなど用途限定。健康効果の保証や日常的な飲用推奨を意味しない | 摂取目的での使用は用量や用途の基準逸脱に注意。飲用安全性の包括保証ではない | 厚生労働省 食品添加物制度 |
| 広告・効能表現の規制 | 医薬品等適正広告基準および薬機法の規制対象 | 疾病の治療や予防を暗示する断定的表現は不可。体験談の誇張も問題になり得る | SNSや販売説明での効果主張に注意。医薬品と誤認させない表現が求められる | 厚生労働省 医薬品等適正広告基準(PDF) |
| 化粧品の基準・表示 | 薬機法下の化粧品基準および表示ルールに従う | 成分規制や配合上限、表示事項などが定められている | 輸入・購入時は表示事項を確認。未承認の効能表示や不十分な表示に注意 | 厚生労働省 薬機法関連情報 |
| 医療用途との線引き | 臨床用途は医療の管理下で評価される領域 | 一般販売の精油は医療の代替ではない。医療効果の主張は規制対象 | 症状がある場合は医療機関で相談。精油は補完的に安全に使用する | PMDA 医薬品等の範囲に関する基準(PDF) |
消費者庁からの注意点


消費者庁は過去に何度も、マルチ商法(連鎖販売取引)に関する注意喚起を行っています。違法ではないとしても、誤解を招く広告や強引な勧誘手法が問題になることが多いためです。特に「断ってもしつこく勧誘される」「商品の効果を誇張して説明された」という事例は、ドテラ関連でも少なくないと言われています(出典:消費者庁「マルチ商法に関する注意喚起」)
さらに、契約や解約を巡るトラブルも報告されています。例えば、定期購入の仕組みを十分に理解しないまま登録してしまい、解約がスムーズにできなかったケースや、返品対応がスピーディに行われなかったケースです。ネットワークビジネス特有の仕組みとして、紹介者を通じてしか手続きができない場合もあり、消費者が不利な立場に置かれることがあるのです。
消費者庁は「契約内容や販売方法に少しでも不審を感じたら、すぐに消費生活センターに相談してほしい」と呼びかけています。つまり、契約前に冷静に判断するための情報収集が欠かせないということです。安易な参加は、想定外のトラブルに巻き込まれるリスクを高める可能性があります。
| 注意点 | 法的位置づけ・権利 | 典型的な問題例 | 取るべき対応 | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|
| クーリング・オフ | 連鎖販売取引は契約書面受領日から20日間のクーリング・オフが可能とされています | 勧誘直後に勢いで申込・支払いをしてしまったが、冷静に考えると不要だった | 書面または電磁的方法でクーリング・オフ通知を送付し、支払済み代金の返還と引取りを求める | 消費者庁 特定商取引法ガイド パンフレット/消費者ホットライン 188 |
| 不実告知・断定的判断の提供の禁止 | 特定商取引法により、事実と異なる説明や「必ず儲かる」等の断定トークは禁止されています | 医療効果を断定する発言や、収益を誇張して参加を急がせる | 勧誘内容のメモ・スクリーンショットを保存し、契約前ならきっぱり断る。契約後はクーリング・オフや相談窓口へ | 消費者庁 事例で学ぶ(広告規制) |
| 迷惑・執拗な勧誘の禁止 | 不招請・再勧誘などの迷惑行為は規制対象。勧誘を受ける意思がない旨を示した後の継続勧誘は問題になります | 断っているのに繰り返し電話やDMが届く、長時間居座り型の勧誘 | 「これ以上の連絡は不要」と明確に伝え記録を残す。改善しなければ相談窓口へ通報 | 消費者庁 事例で学ぶ(勧誘規制) |
| 解約・返品の取り扱い | クーリング・オフ期間経過後でも、一定条件で中途解約・返品が可能な場合があります | 定期購入の仕組みを理解せず登録し、解約窓口が分からない・返品が受け付けられない | 契約書面の解約・返品条項を確認し、事業者への連絡履歴を残す。条件が不当と感じたら公的窓口で助言を受ける | 消費者庁 特定商取引法ガイド Q&A/事例で学ぶ(トラブル対応) |
| 相談・通報体制 | 全国の消費生活センターや消費者ホットライン188で助言・あっせんの案内を受けられます | 勧誘・契約・解約・返金で行き詰まり、事業者と話が平行線 | 188へ電話して最寄りの消費生活センターにつながり、契約書ややり取りの記録を持参して相談 | 消費者庁 消費者ホットライン 188/消費者庁 公式サイト |
ドテラやめたほうがいいと判断する前に知ること


- コンプライアンス違反の事例について
- 勧誘がしつこいと言われる理由
- 友達なくすリスクとは
- ネットワークビジネスの仕組みを解説
- ネット上で見られる評判まとめ
| 確認ポイント | 要点 | 参考情報(公式) | チェック項目 |
|---|---|---|---|
| 会員種別・費用条件(WA/WC・LRP・PV) | WA(ウェルネスアドボケイト:紹介・報酬可)とWC(ホールセールカスタマー:割引購入のみ)で権限が異なる。報酬受領には毎月のLRP(ロイヤリティプログラム)やPV条件の有無・数値を必ず確認 | doTERRA Japan 公式サイト doTERRA Global | 100PVなどの必須条件の有無と金額換算の目安、登録料・年会費、LRPの変更・停止・解約手順を事前確認 |
| 法令・広告規制(薬機法・特定商取引法) | 未承認品に医療効果を示唆する表示は薬機法の規制対象。連鎖販売取引では不実告知や迷惑・執拗な勧誘が特定商取引法で禁止 | 厚生労働省(医薬品等の広告規制) 消費者庁 特定商取引法ガイド | 医療効果を断定する表現を使わない・使わせない。収益や再現性の誇張説明の有無、説明資料や契約書の保存 |
| 安全な使用方法(飲用・希釈・対象者) | 精油は高濃度。飲用や原液塗布はリスクがあるとされ、使用は希釈やパッチテストなどガイドラインの順守が前提。乳幼児・妊産婦・持病・ペットは特に慎重 | 公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ) 厚生労働省 | 飲用を勧められていないか、希釈濃度と使用量、子ども・ペットへの可否、体質・薬との相互作用の確認 |
| 収益構造の現実(紹介要件・時間投資) | 報酬は紹介組織の購買に依存。自己購入費や活動経費が先行するため、黒字化には継続的な紹介・教育・時間投資が必要。期待収益の根拠を数値で把握 | 消費者庁 事例で学ぶ(勧誘・収益誇張) | 月の自己負担総額(製品・移動・会費等)と見込み報酬、損益分岐の人数・PV、活動に割ける時間の現実性 |
| 解約・返品・相談窓口(20日クーリング・オフ・188) | 連鎖販売取引は契約書面受領から20日間のクーリング・オフ可。期間経過後でも条件次第で中途解約・返品が可能な場合あり。困ったら公的窓口へ | 消費者庁 特定商取引法ガイド Q&A 消費者ホットライン 188 | 解約・返品条件と手順、通知方法(書面・電磁的方法)、期限管理、やり取りの証拠化、困ったら188に相談 |
コンプライアンス違反の事例について


ドテラに限らず、エッセンシャルオイルや健康関連商品の販売においては、コンプライアンス違反の事例が複数報告されています。典型的なのは「薬機法違反」と呼ばれるケースです。薬機法では、医薬品として承認されていない商品について「病気が治る」「症状が改善する」といった効能をうたうことを禁じています。
過去には、ドテラの販売員が「風邪が治る」「コロナに効く」といった表現で商品を紹介し、薬機法違反に該当すると指摘された事例もありました。たとえ企業本体が直接そうした表現をしていなくても、販売員個人の発言が問題視され、結果的に企業全体のブランドイメージに悪影響を及ぼすことになります。
さらに、強引な勧誘や説明不足によるトラブルは「特定商取引法」に抵触する可能性もあります。特定商取引法では、勧誘の際に不実の告知や誇張した説明を禁じており、違反が認められれば行政処分や業務停止命令につながることもあります(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」)
このような事例が公になれば、一般の消費者にとって「やめたほうが安心」と感じるのは自然なことです。ブランドの信用は一度失えば回復が難しく、コンプライアンス遵守がどれだけ大切かを示す結果となっています。
| 事例/リスク(適用法令) | NG表現・行為の具体例 | 公式根拠・ガイドライン(一次情報) | 想定される対応・注意点 |
|---|---|---|---|
| 未承認品に医療効果を示唆(薬機法) | 「◯◯が治る」「コロナに効く」「飲めば改善」など医薬品的効能の断定や飲用推奨と受け取れる説明 | 厚生労働省 医薬品等適正広告基準 厚生労働省 医薬品等の広告規制 | 効能の断定・治療効果の暗示は避ける。飲用・原液塗布の安全保証は行わない。説明は香り用途等に限定し、使用上の注意と併記 |
| 不実告知・執拗な勧誘等(特定商取引法:連鎖販売取引) | 断っている相手への再勧誘、利益の過度な強調、購入や契約の強要、経費を伏せた説明 | 消費者庁 連鎖販売取引のルール 消費者庁 事例で学ぶ 勧誘トラブル | 勧誘の適正手順を徹底。断りの意思表示後は再勧誘しない。収益性・費用は数値で正確に説明し、書面を交付・保管 |
| 誇大広告・有利誤認(景品表示法) | 「世界最高品質」「必ず稼げる」「今だけ半額で実質無料」等、根拠のない品質優良・価格有利表示 | 消費者庁 景品表示法 消費者庁 表示適正化に関する指針 | 比較・実証データを事前に用意し、主観や体験談を根拠化しない。割引や特典は条件・期間を明確化 |
| クーリング・オフ妨害/返品拒否(特定商取引法) | 20日間のクーリング・オフ妨害、解約フォームを隠す、返品条件を不当に厳格化する | 消費者庁 特定商取引法ガイド Q&A 消費者庁 クーリング・オフ | 書面(電磁的方法含む)でのクーリング・オフを妨げない。解約・返品手順と期限・費用負担を明示し、迅速に処理 |
| 安全・品質表示の不適切表示(景品表示法等) | 「飲用安全」「オーガニック認証取得」など、実在しない認証や基準を連想させる表現、ラベルの不正確な原産地・成分表示 | 消費者庁 表示全般の考え方 消費者庁 不当表示の未然防止 | 第三者認証は名称・発行主体・範囲を正確に記載。添加物や用途は公的基準に沿って表示し、誤認を招く図案や用語を避ける |
勧誘がしつこいと言われる理由
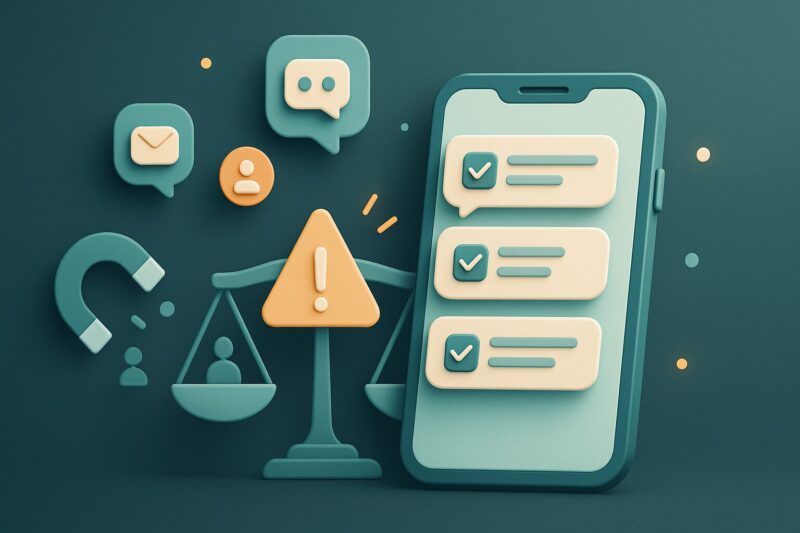
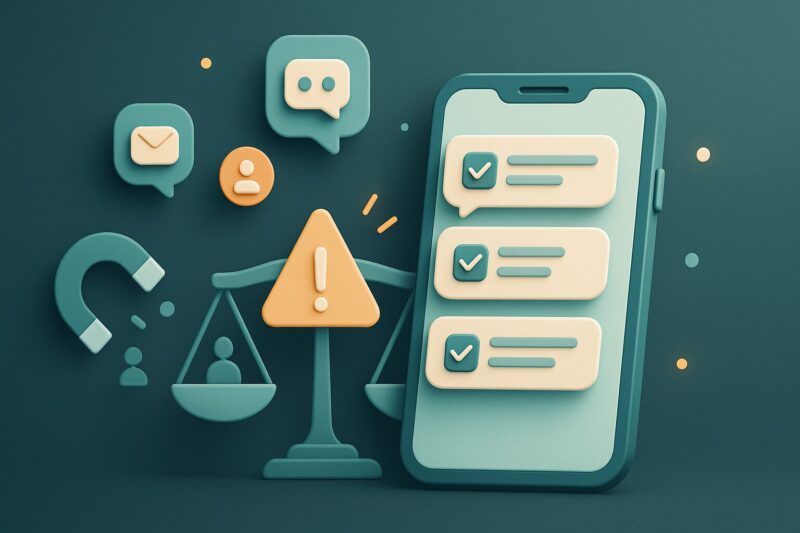
ドテラの会員制度は、新規会員を増やすことによって報酬が上がる仕組みを採用しています。この仕組みはネットワークビジネス(連鎖販売取引)の典型的な特徴であり、参加者が積極的に勧誘を行う強い動機を持つことになります。そのため、一度断っても繰り返し勧誘される、いわゆる「しつこい」と感じられるケースが多発しています。
特に問題となりやすいのは、身近な関係を通じての勧誘です。ママ友や職場の同僚、親戚といった距離の近い人からの誘いは、断ることが心理的に難しくなりがちです。また「健康に良いから家族も使ってほしい」「将来のために一緒にやろう」といった、情に訴えるトークが用いられることも多く、相手にプレッシャーを与える原因となっています。
消費者庁が公開している過去の事例にも「断ってもしつこく勧誘され、生活に支障をきたした」という相談が寄せられています(出典:消費者庁 消費生活相談データベース )。こうした背景から、強引な勧誘は消費者に警戒され、信頼を失う一因になっているのです。
| 要因・背景 | 具体例・よくある場面 | 関連法令・公式ルール(一次情報) | 受け手の対処・手順 | 相談窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 紹介人数や購入量に連動する報酬設計 | 「あと◯人紹介でボーナス」「毎月◯PV達成が必要」と購入・勧誘を繰り返し促す | 消費者庁 連鎖販売取引のルール 消費者庁 勧誘トラブル事例 | 収益条件と自己負担を数値で確認し、参加意思がなければ明確に断る。以後の連絡は不要と伝える | 消費者庁/ 消費生活センター(188) |
| 身近な人間関係を使う勧誘手法 | ママ友・同僚・親族の集まりで製品体験会→その場で入会・定期購入を迫られる | 特定商取引法(連鎖販売取引)での勧誘規律 不実告知・困惑させる勧誘の禁止 | 会合の目的を事前確認。入会・購入は即断しない。勧誘は一切受けない旨をはっきり伝える | 国民生活センター/#9110(警察相談) |
| 再勧誘・時間帯配慮の欠如 | 断った後も電話・DM・訪問が続く。深夜や早朝、勤務時間中の連絡 | 消費者庁 相談・救済の流れ クーリング・オフ制度 | 時刻・手段・相手名を記録し、再連絡禁止の意思表示を書面/メールで残す。必要に応じ着信拒否 | 188(最寄りの消費生活センター)/迷惑行為は#9110 |
| 利益の誇大表示・リスク非開示 | 「誰でも簡単に月◯万円」「在庫なしでノーリスク」等の有利誤認表示 | 景品表示法(有利誤認の禁止) 連鎖販売取引の説明義務 | 費用・条件・成功率の根拠資料提示を求める。示せない場合は契約しない | 188(消費生活センター)/自治体の消費生活相談窓口 |
| SNS・DMによる反復的な接触 | Instagram・LINE・メールで体験談やイベント告知が高頻度で届く | ネット勧誘での留意点(消費者庁) | メッセージは未読スルーではなく「今後の案内は不要」と明記。ブロック・通報設定も活用 | 各SNSの通報機能/188(不当表示や執拗な勧誘の相談) |
友達なくすリスクとは


ドテラに参加した人の中には、結果的に人間関係が悪化し「友達をなくした」と感じるケースが少なくありません。これはビジネスモデル上、知人や友人に商品を勧めることが中心となるため、親しい関係が「販売の対象」として扱われてしまうからです。
例えば、仲の良かった友人が急に製品の話やビジネスの勧誘ばかりするようになり、以前のように気軽に会話できなくなることがあります。断る側も「気まずさ」を感じて距離を取るようになり、結果的に疎遠になることが多いのです。さらに、「断ったら関係が冷えた」「勧誘を避けるために集まりに参加しなくなった」といった声も見られます。
このような人間関係のトラブルは、ドテラをやめた理由として頻繁に挙げられています。もともと副収入を得たい、健康的な生活をしたいと考えて始めたことが、逆に孤立感やストレスを生む結果になるのは本末転倒です。特に家族や長年の友人との信頼関係が壊れてしまうリスクは深刻であり、ドテラの活動を続けるかどうかを考えるうえで大きな懸念点となっています。
| 要因 | 具体的な場面 | 想定される影響 | 対処のコツ | 公的情報(一次情報) |
|---|---|---|---|---|
| 関係の非対称化(ビジネス優先) | 雑談や近況報告より製品説明や登録案内が中心になり、会うたび勧誘テーマになる | 信頼の低下、距離を置かれる、コミュニティからの孤立感 | 勧誘は受けない方針を先に宣言し、ビジネスの話題は断ると明確に伝える | 国民生活センター 若者に広がるモノなしマルチ商法 |
| 度重なる勧誘・DM連絡 | SNSやメッセージでの招待、セミナー誘致、断っても繰り返し送られる | 心理的負担、既読スルーやブロックによる関係断絶 | 再勧誘の禁止等のルールを示しつつ、書面やメッセージで「今後の勧誘は不要」と記録を残す | 消費者庁 特定商取引法 連鎖販売取引のルール |
| 誇大な効能表現による価値観の対立 | 体調改善や病気予防など医薬品的な表現を巡る議論で口論に発展 | 医療・健康観の違いが露呈し、長年の友人関係にひび | 薬機法の範囲を確認し、健康情報は公的根拠の有無で線引きして会話を整理 | 厚生労働省 医薬品等の広告規制 |
| 金銭絡みの摩擦 | 共同購入や立替、ノルマ充足のための購入要請で負担が偏る | 返金トラブル、未収の発生、関係悪化 | 金銭の貸し借りは行わない・共同購入は不可と事前合意、取引は必ず個別・自己決済 | 消費者庁 連鎖販売取引の相談例 |
| SNSでの公私混同による反発 | タイムラインが勧誘投稿で埋まり、知人がミュート・フォロー解除 | 関係の希薄化、オフラインの誘い減少 | ビジネス投稿の公開範囲を分ける、相手の同意なくDM勧誘しない | 消費者庁 消費者ホットライン188/国民生活センター 188案内 |
ネットワークビジネスの仕組みを解説
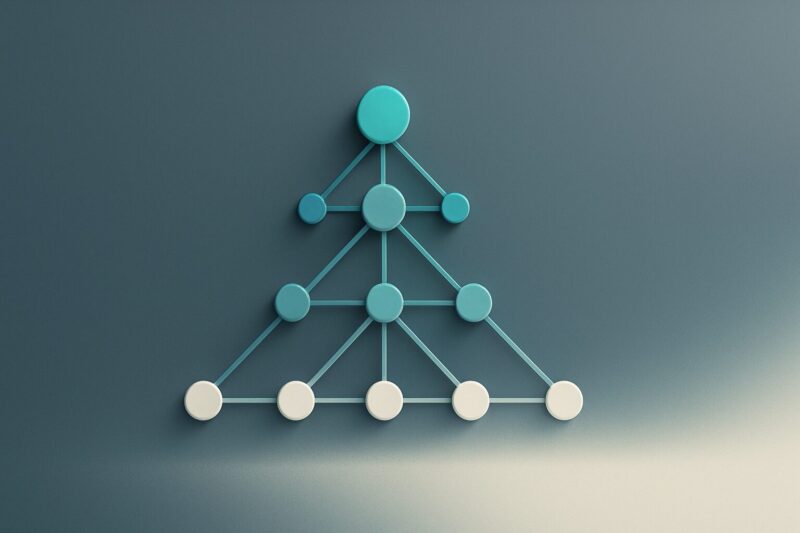
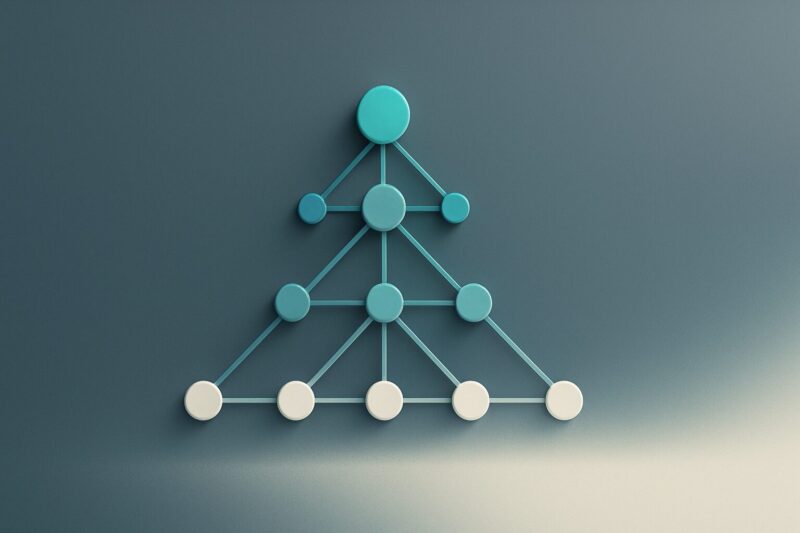
ドテラのビジネスモデルは、ネットワークビジネス(MLM:マルチレベルマーケティング)に分類されます。この仕組みでは、自分が新規会員を紹介すると、その人が購入した商品の一部が報酬として還元されます。さらに、その会員が別の人を紹介すれば、その下の階層の売上からも一定の割合が報酬として分配されるため、組織を拡大すれば収入も増える構造になっています。
表にすると以下のようなイメージです。
| 役割 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| WA(ウェルネスアドボケイト) | 商品を割引購入・販売・新規勧誘が可能 | 報酬を得られる | 継続購入が必要、勧誘必須 |
| WC(ホールセールカスタマー) | 割引価格で商品を購入できる会員 | 安く買える | 報酬は得られない |
| 要素 | 公式の位置付け・仕組み | 参加/受給の主な条件 | 想定メリット | リスク・注意点 / 公的・公式情報 |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分(WA / WC) | ウェルネスアドボケイト(WA)は販売・紹介と報酬受領が可能、ホールセールカスタマー(WC)は割引購入のみ | 登録時に区分を選択(後日変更可とされる国/地域あり) | WAは紹介活動で報酬機会、WCは会員価格で購入できる | 公式:dōTERRA Japan|会員種別と登録 |
| 定期購入(LRP)とPV | LRP(Loyalty Rewards Program)はポイント付与の定期購入。日本公式情報では月100PVのLRPが各種特典・ボーナス要件の基礎として案内 | 毎月100PVのLRP注文、期日や閾値(例:125PVでプロモ対象)などのローカル条件を順守 | 送料相当ポイント、商品ポイント還元、プロモ対象などが受けられる | 公式FAQ:dōTERRA Japan|FAQ 例:100PVで無料配送、125PVでプロモ(時期・内容により変動) |
| 報酬タイプ(ファストスタート / ユニレベル) | 登録初期は紹介者側にファストスタート、一定期間後はユニレベルで組織ボリュームに基づき月次支払い | 国/地域の報酬規程に準拠(例:初期60日間はユニレベル対象外でFS優先など) | 初期紹介のインセンティブと継続組織構築の両輪で収益化を図る設計 | 公式(英語):FAQ About Commissions 公式(日本):報酬プラン(概要) |
| Power of 3 ボーナス | 自分とフロントライン3名がそれぞれ100PV以上のLRPを行い、チーム合計600PV等の条件を満たすと定額ボーナス | 本人100PV LRP + 直下3名100PV LRP + チーム600PV(段階により条件・支給額が変動) | 小規模チームでも達成しやすい設計で固定額が得られる | 公式(日本):報酬プラン(Power of 3) |
| 法規制の枠組み | 日本では連鎖販売取引(特定商取引法)の対象。勧誘・表示・契約手続に厳格な規制がある | 不実告知・誇大広告の禁止、クーリング・オフ、再勧誘禁止などの遵守 | 適切に運用すればトラブル抑制と継続運営に資する | 公的情報:消費者庁|連鎖販売取引 参考:経産省|特定商取引法 概要 |
ただし、このモデルには大きな落とし穴があります。収入を得るためには、自分自身も毎月一定額(例えば100PV=約12,000円以上)の購入が必要です。そのため、思うように紹介者が増えなければ「支出だけが増えて収入はわずか」という状況に陥りやすいのです。
実際に、多くの人が「儲かるどころか赤字になった」と語っており、ネットワークビジネス全体の課題でもあります。理論的には組織を拡大すれば収益が増えるはずですが、参加者全員が成功できるわけではなく、構造的に上位の人ほど有利になっています。これを理解せずに始めると「想像と現実のギャップ」に苦しむことになりかねません。
ネット上で見られる評判まとめ


ドテラに関する評判は、インターネット上で二極化しています。ポジティブな声では「香りが良くリラックスできた」「寝つきが良くなった気がする」「スキンケアや掃除に使えて便利」といった、製品の使用感やライフスタイルへの取り入れやすさが評価されています。アロマオイル自体は古くから利用されているものであり、そのリラクゼーション効果を実感する人がいるのは確かです。
一方で、ネガティブな評判も数多く報告されています。「オイルの価格が高すぎる」「定期購入の負担が重い」「勧誘が強引で不快だった」「やめたいのに退会手続きが複雑」といった声は、SNSや口コミ掲示板でも目立ちます。特に、人間関係を巻き込む形での勧誘については厳しい批判が多く、ママ友や同僚との関係が悪化したという事例が複数見られます。
また、「期待したほど効果がなかった」という意見も少なくありません。アロマオイルは医薬品ではなく、厚生労働省から効能を保証されているわけでもないため、健康改善や病気予防の効果を期待すると落胆するケースがあります。さらに「高い金額を払ってまで買う必要があるのか」という疑問も、口コミでは繰り返し挙げられています。
このように、ネット上の評判からは「製品自体は悪くないが、価格や勧誘方法、ビジネスモデルに不満を持つ人が多い」という全体像が浮かび上がります。良い面と悪い面を見比べながら、自分にとって本当に必要かどうかを判断することが大切です。
| 評価軸 | ポジティブ意見の代表例 | ネガティブ意見の代表例 | 関連公式情報(参考) | 注意点・補足 |
|---|---|---|---|---|
| 香り・使用感 | リラックスしやすい、就寝前に落ち着く、掃除やスキンケア用途で使いやすい | 香りが強すぎて頭痛がする、家族が苦手に感じる、好みが分かれる | 製品品質(CPTG):dōTERRA Japan|品質 ロット検査情報:Source to You | 香りの感じ方は個人差が大きい。初回は少量・短時間で様子を見る |
| 価格・コスパ | 会員価格やポイント還元で割安感がある、プロモーションでお得に入手できる | 単価が高め、定期購入で出費がかさむ、長期的に家計負担になる | LRP(定期購入):dōTERRA Japan|FAQ 会員区分:会員種別 | 月ごとの購入目安や予算上限を事前に設定し、消費ペースを把握する |
| 安全性・使用方法 | 成分検査やトレーサビリティを掲示、希釈・芳香など基本的な使い方で安心しやすい | 飲用や原液塗布の推奨に戸惑い、肌トラブルや刺激感を訴える声がある | 医薬品等の広告規制:厚生労働省 AEAJ安全ガイド:日本アロマ環境協会 | 医薬品ではないため効能表現に注意。肌には必ず希釈し、パッチテストを行う |
| ビジネス・勧誘 | コミュニティで学べる、副収入の可能性、製品のシェアが楽しいという声 | 勧誘がしつこいと感じる、収益が伸びない、関係悪化のきっかけになる | 報酬プラン:dōTERRA Japan 連鎖販売取引:消費者庁 | 勧誘は法令順守が前提。再勧誘禁止や不実告知の禁止などを必ず確認する |
| 解約・サポート | オンライン手続きやカスタマーサポートで解約・返品が可能と案内 | 定期購入停止や返品条件が分かりにくい時期がある、連絡が手間 | お問い合わせ:dōTERRA Japan 返品ポリシー:返品・交換 | 注文締切やPV条件、返品期限・状態を事前に確認し、証跡を残す |
まとめとしてドテラやめたほうがいいか考える
ここまで解説してきた内容を踏まえると、ドテラに関わるかどうかを考える際には、次のようなポイントを冷静に整理する必要があります。以下は、記事の要点を整理したものです。
- ドテラをやめた理由として経済的負担が大きい
- 続けた結果として後悔の声も多く見られる
- 飲用や塗布など使用法に潜む危険性がある
- 厚生労働省は医薬品として認可していない
- 一部は食品添加物だが効能を保証していない
- 消費者庁は強引な勧誘に注意を呼びかけている
- 契約や解約に関するトラブル事例がある
- コンプライアンス違反とされる販売事例が報告されている
- 勧誘がしつこいと感じる人が多い
- 勧誘によって友達なくすリスクがある
- ネットワークビジネスの仕組みは上位が有利になりやすい
- 継続購入のノルマが赤字の原因になりやすい
- 製品の評判は良い声と悪い声が混在している
- 香りやリラクゼーション効果を評価する声もある
- 高価格や効果への疑問から批判が多い
これらを総合すると、ドテラに魅力を感じる点があったとしても、リスクや負担の大きさを無視することはできません。健康や人間関係、お金に関わる判断である以上、十分な情報を集めた上で、自分や家族にとって最適な選択をすることが求められます。