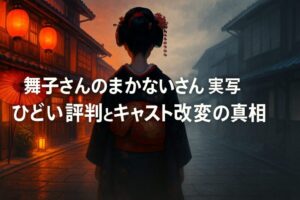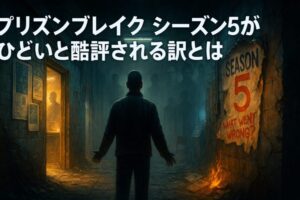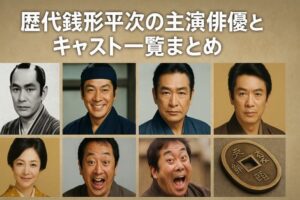テレビを見ていてふと疑問に思った方も多いのではないでしょうか。「コッシーどうやって動いてるの?」と。
NHK Eテレの人気番組『みいつけた!』に登場するコッシーは、まるで生きているかのように自由自在に動く“コッシー椅子”。
その不思議な動きの仕組みについて、ネット上では「ラジコンで動かしているのでは?」「もしかしてCG?」といった様々な説が飛び交っています。
特に注目されるのは足の裏の構造。ここに動きの秘密が隠されているという声も多く、細部まで観察する人も少なくありません。
「コッシーどうやって動いてる?」という素朴な疑問に応えるべく、作り方のヒントや製作技術、さらには声を担当している人物にまで迫ります。
この記事では、コッシーの動きに関する情報をわかりやすく、そして楽しく紹介していきます。
- コッシーの動きの仕組みとして有力なラジコン操作説の詳細
- CGやテグスなど他の動作方法の可能性と限界
- コッシー椅子の形状や足の裏にある工夫から見る制約と特徴
- 類似キャラ(うーたん・ゴットン)との比較から見える演出技術
コッシーどうやって動いてる?仕組みを徹底解説


- コッシーの動きはラジコン操作が有力
- CGで動いてる可能性はある?
- コッシーの足の裏に仕掛けがある?
- テグスやワイヤーによる物理的な動き
- コッシー椅子の形状からわかる制約
- コンサートでの動きから見た仕組みのヒント
コッシーの動きはラジコン操作が有力


コッシーの動きについて最も有力とされているのが「ラジコン操作説」です。テレビやステージ上で見せるスムーズで自由自在な動きは、ラジコンによって遠隔操作されているからこそ可能なのではないかと、多くの視聴者が考えています。
その理由として、まず注目されているのがコッシーの足元です。番組の映像やコンサートの映像をよく見ると、足の下部にわずかな隙間が確認できることがあります。その隙間には小さな車輪のようなものが見え隠れしており、まるでラジコンカーのように床を滑るように動いているのです。
また、コッシーは目や眉毛まで細かく動かします。これらの動きがすべて人の手ではなくリモコンで操作されていると考えると、複雑な動きにも納得がいきます。特にステージショーなどでは、コッシーが他のキャラクターとぴったり息を合わせて動いている場面もあり、タイミングの正確さから見てもラジコン制御の可能性は高いと言えるでしょう。
ただし、どれほど有力な説であっても、NHK側から公式に「ラジコンで動かしています」とは発表されていません。これは子どもたちの夢を壊さないための配慮かもしれませんが、大人の目線では「どうやって?」とつい技術的な裏側が気になってしまうものです。
実際に、コッシーの製作にはロボットや着ぐるみなどを手がける専門会社「アレグロ」が関わっていることもわかっており、技術力の高さを裏付けています。つまり、コッシーのなめらかな動きは、高度なラジコン技術と制御システムによるものだと考えるのが自然なのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 操作方式 | ラジコンによる遠隔操作が有力 |
| 動力源 | 足元に内蔵された小型モーター |
| 制御方法 | 無線リモコンによる操作 |
| 操演技術 | 専門会社「アレグロ」による造形と制御 |
| 補足情報 | 目や眉の表情もリモコンで制御可能 |
CGで動いてる可能性はある?


コッシーの動きがCG(コンピューターグラフィックス)によるものではないか、という声も一部では見かけますが、その可能性はかなり低いと考えられます。
というのも、コッシーはテレビ番組だけでなく、公開コンサートやイベントでも実際に動いています。観客の目の前で滑らかに動き、他のキャラクターと一緒に踊ったりやりとりしたりする様子は、CGでは再現できない“生の存在感”があります。観客の目の前でCGを使うことは現実的ではありませんし、そもそもCGならではの映像特有の不自然さも見当たりません。
また、テレビ番組での映像を見ても、グリーンバックや合成による違和感は一切感じられません。例えば影の付き方や他のキャラクターとの自然なやりとり、床との接地感など、CGでは難しいリアルな演出がしっかりとされています。
もちろん、編集の段階で一部に映像効果が加えられていることはあるかもしれません。しかし、基本的なコッシーの動きがCGで作られているという可能性は極めて低く、現実には存在するロボット的な仕組みや操演によって成り立っていると考えるほうが自然です。
つまり、コッシーの動きがCGで作られているという説はロマンこそあれ、現実的な証拠がなく、あくまで憶測にとどまるもの。子どもたちにとっては「生きているように見える」ことが大切で、実際にその場で動くコッシーの姿こそが、多くのファンの心をつかんでいる理由なのです。
CG制作の基礎や応用技術について、大学の教育内容から理解を深めたい方は、こちらの資料大阪電気通信大学 パンフレット2023(PDF)をご覧ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| CG使用の可能性 | 極めて低い。コンサートなどの生出演では実物が動いているため |
| テレビ映像での確認 | 影や接地感が自然で、グリーンバックや合成の痕跡は見られない |
| 動きのリアルさ | 他キャラとの連携や床を滑るような動作は現実的でCGに見えない |
| 編集の可能性 | ごく一部で演出効果としてCGを加えることはあり得る |
| 結論 | 主な動きは実物の機械・操演によるものであり、CGは使われていない |
コッシーの足の裏に仕掛けがある?


コッシーの動きを観察していると、特に注目されるのが「足の裏」です。普段、番組を見ているだけではあまり気づかないかもしれませんが、実はこの部分に秘密が隠されているのではないかと考える人が多くいます。
その理由のひとつに、足の裏に小さなタイヤのようなものがついているように見えるという点があります。特に動いているとき、コッシーが床を滑るように動く様子は、まるで電動の車輪がついているかのようです。実際に映像をよく観察してみると、足元が少し浮いているように見える場面や、床との接触部分が不自然に隠されている場面もあり、「もしかしてここに動力源があるのでは?」という疑問が自然と湧いてきます。
また、足元をあえて見せないカメラアングルが多いことも、視聴者の想像をかき立てます。もし何かしらの機械や装置が仕込まれているとしたら、足の裏を映さないことでその存在を隠しているのかもしれません。これはテレビ番組ならではの“演出”とも考えられますが、技術的な工夫がされている可能性も十分に考えられます。
とはいえ、実際に足の裏に何があるのかは公表されていません。そのため、視聴者の間では「ラジコン操作なのか?」「内部にモーターがあるのか?」といった議論が続いています。子どもたちに夢を与えるキャラクターだからこそ、仕掛けの存在をあえて曖昧にしているのかもしれませんね。
このように、足の裏に注目すると、コッシーの不思議な動きに少し近づけるような気がして、つい目を凝らしてしまいます。まさに、細部にこそ“秘密”が隠れているのかもしれません。
テグスやワイヤーによる物理的な動き


一部のファンや視聴者の間では、「コッシーの動きはテグスやワイヤーで引っ張っているのではないか」という説も語られています。特に、初期の『みいつけた!』を思い返すと、その動きが少しぎこちなく見えることがあり、機械仕掛けではなく人の手によるアナログな操作を疑う声が出るのも不思議ではありません。
テグスとは、釣り糸のように細くて透明な糸のことです。テレビの舞台セットや人形劇などでよく使われる素材で、視覚的にはほとんど目立ちません。この糸を使ってキャラクターを引っ張れば、まるで自力で動いているかのように見せることができるのです。
実際、コッシーが画面の中で移動する際に、不自然な引っ張られ方や急な動きの変化が見られる場面もあります。それがワイヤーやテグスによるものだとしたら、辻褄が合う動きだと感じる人もいるでしょう。特に足元が見えない場面では、そうしたアナログ操作の可能性が高いと考える向きもあります。
ただし、テグス操作には限界があります。長距離を滑らかに動かすのは難しく、コントロールもかなり手間がかかります。最近のように複雑な動きやキャラクター同士のタイミングの合ったやりとりを実現するには、より進化した仕組みが必要になるため、現在ではこの方式は使われていない可能性が高いです。
とはいえ、昔ながらのアナログ技術が今でも使われていたら、それはそれで夢がありますよね。どこか懐かしさを感じるテグス操作の魅力は、視聴者にとって「どうやって動いてるの?」という好奇心をさらにかき立てる一因になっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用される素材 | テグス(透明な釣り糸)や細いワイヤーを使用することがある |
| 操作方法 | 舞台裏やセットの外から人が手動で引っ張る仕組み |
| 活用される場面 | 初期の『みいつけた!』など、スタジオ内での簡単な動きに使用 |
| 制限・デメリット | 長距離や複雑な動きは困難で、動きがぎこちなくなることがある |
| 現在の使用状況 | 現在はあまり使われておらず、ラジコンなどの進化した仕組みに移行していると考えられる |
コッシー椅子の形状からわかる制約


コッシーの動きを考えるとき、まず注目すべきはその独特な「椅子の形状」です。一見すると普通の青い椅子に顔がついているだけのように思えますが、その見た目には動き方を制限する要素がたくさん含まれています。
まず、コッシーの脚部は短くて安定感のあるデザインです。これは、転倒しにくくするための工夫とも取れますが、逆に言えば、動き回る際の機敏な動作や方向転換には不向きです。また、四角い座面部分は広く、内部に機械や装置が入っていそうな余裕は感じられるものの、見た目を崩さずに動力を仕込むには限界があるようにも思えます。
さらに、背もたれ部分は高くはありませんが、動きの際にバランスをとるための重心設計としては考慮されているはずです。しかし、あの高さと形では、たとえば人が中に入るには難しいという印象を受けます。つまり、内部に人が隠れて操作している可能性は低そうです。
こうして見ると、コッシーはあくまで「椅子らしさ」を崩さずに動かす必要があるため、その見た目自体がある意味、動き方に大きな制約を与えているのです。その中で、どのようにスムーズな動きを実現しているのかを考えると、ますます仕組みの謎に惹かれてしまいます。
コンサートでの動きから見た仕組みのヒント


コッシーはテレビ番組だけでなく、NHK主催のコンサートやイベントにも登場することがあります。そうした「生の舞台」での動きを観察すると、普段テレビではわからないようなヒントが見えてくるのです。
テレビ放送では、カメラワークや編集によって足元を映さずに自然な動きを演出することが可能ですが、コンサートのように観客の目が四方八方から向けられる舞台では、そう簡単にごまかせません。それにもかかわらず、コッシーはステージ上でスムーズに移動し、ときには他のキャラクターと息の合ったパフォーマンスを披露します。
このことから考えると、やはり何らかの無線操作による自動走行やリモコンでの制御が行われている可能性が高いと言えそうです。特に、ステージ全体を自由に動き回れることから、ワイヤーやテグスのような制限のある仕掛けでは対応できないと考えられます。
また、ステージでは照明や演出のタイミングとも連動して動いているため、ある程度プログラム化された動きである可能性も否定できません。ただし、観客からは動かす人や機械の存在は見えないため、そういった技術がいかに巧みに隠されているかがよくわかります。
コンサートは、コッシーの“動きの仕組み”を探る上で貴重な観察の場です。間近で見れば見るほど、「どうやって動いてるの?」という疑問は深まりますが、それと同時に子どもたちの夢を壊さないように工夫されていることにも気づかされ、製作スタッフのこだわりに感心させられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登場場所 | NHK主催「ワンワンといっしょ!夢のキャラクター大集合」などのコンサート |
| 動きの特徴 | 客席からも見える状態で、自然に前後左右に移動・停止・回転を行う |
| 推定される仕組み | ラジコン式の電動駆動によるリモコン操作やプログラム制御 |
| 操縦の工夫 | 照明演出や他キャラとの連動により、操作している人物や機械が見えないように調整 |
| 観察ポイント | 舞台上でのタイミングの一致や床との接地感が、機械的な精密さを示している |
コッシーどうやって動いてる?類似キャラと比較検証


| キャラクター名 | 登場番組 | 主な動作方式 | 動きの特徴 | 操演方法の違い |
|---|---|---|---|---|
| コッシー | みいつけた! | リモコン操作(ラジコン説が有力) | スムーズな移動、目や眉の細かい動き | 内部に小型モーターや車輪が仕込まれている可能性 |
| うーたん | いないいないばあっ! | 人形劇形式(手による操作) | ぴょんぴょん跳ねる、軽やかな身振り | セットの下から操演者が手で動かしている |
| ゴットン | みいつけた! | 電動モーター+補助的な人力操作 | 直線移動がメイン、重厚感ある動き | 目立たない場所からリモートで制御、場面によっては押して動かす |
うーたんはどうやって動いてる?


うーたんの動きは、一見すると魔法のようで、見ている子どもたちも大人もつい釘付けになってしまいます。ぴょんぴょん跳ねたり、リズムに合わせて体を揺らしたりと、まるで生きているかのような動きが印象的です。しかし、じっくり観察してみると、うーたんの動きには「人の手による操作」が隠されていることがわかります。
うーたんは主に、着ぐるみではなく「人形劇形式」で演じられており、舞台の裏やセットの下から手を使って動かす方法がとられています。特にNHKの『いないいないばあっ!』では、撮影用のスタジオセットが巧みに作られており、操演者(うーたんを動かす人)が見えないようになっています。うーたんの背中に腕を入れ、顔の動きやジャンプ、くるくると回るような動作までも自然に見せる技術は、まさに職人芸です。
また、うーたんの声は別の声優が担当しており、動きと声が絶妙にリンクしていることで、よりリアルで親しみやすいキャラクターとして成り立っています。子どもが「ほんとにいるんじゃない?」と信じてしまうのも無理はありません。
ちなみに、イベントなどの生放送やステージでは、操作する人の動きが直接反映されるため、テレビとは少し違った雰囲気が楽しめることもあります。だからこそ、「どうやって動いてるの?」という疑問は、いつまでも色あせない魅力として残るのでしょう。
ゴットンはどうやって動いてる?


ゴットンは『みいつけた!』に登場するキャラクターの中でも、特にユニークな存在です。見た目は木製の汽車のようで、どっしりとした形をしていますが、そのわりに動きがスムーズでテンポ良く進む様子が印象的です。とはいえ、コッシーやうーたんと違って、ゴットンの動きには少し「機械的な雰囲気」があるのも事実です。
ゴットンがどう動いているのかというと、これまでに公開された映像や目撃情報などを総合すると、「リモコンや電動モーターによる自走」が有力とされています。特に、ゴットンの車輪部分は見た目にも動力が仕込まれていそうな形状をしており、ゆっくり前に進む様子や方向を切り替える動きなどは、機械による制御である可能性が高いです。
また、撮影時のカメラアングルやカット割りによって、動力部分をさりげなく隠している工夫も見られます。たとえば、足元が映らないようにしたり、背景に溶け込ませるような色使いをしたりと、細やかな演出が随所に施されています。
ただし、全てのシーンが完全にリモコン操作というわけではなく、一部では人の手で押して動かしていると推測される場面もあります。特に止まった状態からゆっくり動き出すときなどは、人力によるサポートが入っている可能性もあるでしょう。
ゴットンの動きには、制作側の遊び心と技術力が詰まっていて、知れば知るほど面白さが増していきます。「どうやって動いてるんだろう?」という疑問は、子どもたちの好奇心を引き出すだけでなく、大人にとっても番組の楽しみ方のひとつと言えるのではないでしょうか。
コッシーの声を担当するのは誰?


コッシーの独特な声は、番組『みいつけた!』の魅力をグッと引き立てていますよね。あの明るくてちょっとおちゃめな声を聞くと、子どもだけでなく大人もつい笑顔になってしまいます。そんなコッシーの声を担当しているのは、サバンナの高橋茂雄さんです。
お笑い芸人として活動する高橋さんですが、コッシーの役ではその明るさに加えて、子どもたちに寄り添うようなやさしさや親しみを感じさせる演技が光っています。ただ面白いだけでなく、時には友だち思いでまじめな一面を見せるコッシーの声に、リアルな感情がこもっているのは、高橋さんの演技力あってこそでしょう。
番組が始まった当初から、コッシーの声は変わっていないため、長年見ている視聴者にとってもなじみ深く、安心感のある存在になっています。ちなみに、高橋さんは自身のSNSなどでコッシーについて触れることもあり、番組への愛情も感じられます。
キャラクターにぴったりな声というのは、子ども向け番組ではとても大切な要素です。だからこそ、「コッシーの声って誰?」と気になったときに、その背景を知ることで、番組を見る楽しみもまたひとつ増えるかもしれませんね。
コッシーの作り方や造形の裏側


コッシーは見た目は椅子そのものですが、表情が豊かで自由に動き回る様子に、「どうやって作られてるの?」と興味を持つ人も少なくありません。実際、あのユニークなデザインと動きには、細やかな工夫と職人の技術が詰まっています。
コッシーの本体は、椅子の形をベースにしたぬいぐるみや着ぐるみのような構造になっていて、素材は布やウレタンなど軽くて柔らかいものが使われているようです。これは、万が一子どもが触れたり、ステージ上でぶつかったりしても安全なように配慮されているためです。
また、顔の部分には目や口がついていますが、これも全体のバランスを壊さないように可愛らしくデフォルメされていて、親しみやすい印象を与えます。造形の段階では、動かしやすさも重視されているようで、リモコンや人の手で操作することを前提に作られていると考えられます。
裏側の仕組みについては公表されていない部分も多いですが、テレビやイベントでの映像をよく見ると、コッシーの足元や背面に微妙な開閉部があるなど、操作のための構造が見え隠れすることもあります。そうした「見せない工夫」があるからこそ、キャラクターの世界観を壊すことなく、自然な動きを実現しているのです。
このように、コッシーの造形には見た目の可愛さと動きやすさ、さらには安全性までがしっかりと考えられています。知れば知るほど、画面の向こうにいるキャラクターが、どれだけ丁寧に作られているかが伝わってきて、より愛着が湧いてきますね。
制作会社の技術力が動きを支える


コッシーのようなキャラクターが、まるで命を持っているかのように自然に動く背景には、制作会社の高度な技術力が欠かせません。ただ可愛いキャラクターを作るだけでは、子どもたちの心をつかむことはできません。番組の魅力を最大限に引き出すためには、細部まで丁寧に作りこまれた演出と仕掛けが必要です。
「みいつけた!」を制作しているNHKエデュケーショナルは、長年にわたり教育番組を手がけてきた実績があります。その蓄積されたノウハウを活かし、キャラクターが動くタイミングや視線の方向、表情の変化まで計算された動作が実現されています。コッシーが自然にジャンプしたり、回転したりするのも、背景にある高度な仕組みや精密な調整のおかげです。
また、こうしたキャラクターの動きを支えているのは、決して一つの技術だけではありません。リモコンによる操作、時には人の手による演出、そしてカメラワークとの絶妙な組み合わせなど、さまざまな方法を柔軟に取り入れて、一体感のある映像に仕上げているのです。
見ている私たちは、その完成された映像に自然と引き込まれますが、その裏にはたくさんの試行錯誤と創意工夫があります。このように、制作会社の確かな技術があるからこそ、コッシーの世界は現実感を持って私たちの前に現れてくるのです。
子ども番組における演出の工夫とは


子ども向け番組では、ただキャラクターが登場するだけでなく、「どう動くか」「どう見せるか」も非常に大切です。子どもは大人以上に細かい部分に敏感で、違和感があればすぐに気づいてしまいます。だからこそ、演出の工夫には特別な配慮が求められます。
たとえば、コッシーが話しかけるときには、きちんと相手の方を向いて口が動くように見えるよう調整されています。ほんの一瞬のしぐさや間の取り方も、子どもが感情移入しやすいように計算されているのです。こうした細やかな演出が積み重なることで、キャラクターが本当に「生きている」と感じさせてくれます。
さらに、スタジオのセットもポイントです。視覚的に楽しく、カラフルで親しみやすい空間が広がることで、子どもたちがワクワクしながら番組に集中できるようになっています。また、音楽や効果音も演出の一部として、キャラクターの動きにタイミングよく組み合わされています。
もちろん、大人が見ても面白いと感じられるような仕掛けがあることも、番組が長く愛される理由のひとつです。親子で一緒に楽しめるような演出が施されているため、子どもだけでなく大人も自然と番組に引き込まれます。
こうした演出の工夫が積み重なることで、ただの教育番組ではなく、家族で楽しめる「体験」としての番組が完成するのです。視覚・聴覚・感情すべてを使って楽しむ子ども番組には、想像以上に多くの創意が詰まっています。
「環境教育やリサイクルに関する取り組み事例を通じて、子ども向け番組の演出の工夫について考察したい方は、こちらの資料経済産業省「団体・事業者による3R教育に関する取組事例集」(PDF)をご参照ください。
まとめ:コッシーどうやって動いてる?仕組みと裏側を徹底解説
記事をまとめます。
- コッシーの動きはラジコンによる遠隔操作の可能性が高い
- 足元に小さな車輪のような構造が見えることがある
- ステージ上でも自然に動くためCGの可能性は低い
- 目や眉毛など細かなパーツも動く演出がある
- NHK公式には操作方法について明かされていない
- 制作にはロボットや着ぐるみに強い「アレグロ社」が関与
- 足の裏に機械的な仕掛けがあると推測されている
- 番組では足元をあえて映さないアングルが多い
- 初期のコッシーにはテグスやワイヤー操作の可能性もあった
- 現在のような複雑な動きにはテグスでは対応しきれない
- コッシーの椅子の形状が動作に制限を与えている
- 座面や脚の太さから人が中に入る構造ではなさそう
- コンサートでは全方位から見られるが自然な動きを保っている
- リモコンやプログラム制御による動作の可能性がある
- ゴットンはリモコンかモーターによる自走型が有力
- うーたんは人形劇形式で手動操作されている
- コッシーの声はサバンナ高橋茂雄が担当している
- 本体はウレタンや布などの柔らかい素材で安全に配慮
- 造形には見た目と操作性のバランスが取られている
- スタジオセットや照明もキャラクターの動きを補完している
- 制作会社の高度な技術と演出力で自然な動きを実現している
- 視覚効果や音響も含めた細やかな演出が魅力を支えている
- 子ども向け番組としての演出には特別な配慮がされている
- キャラクターが「生きているように見える」工夫が徹底されている